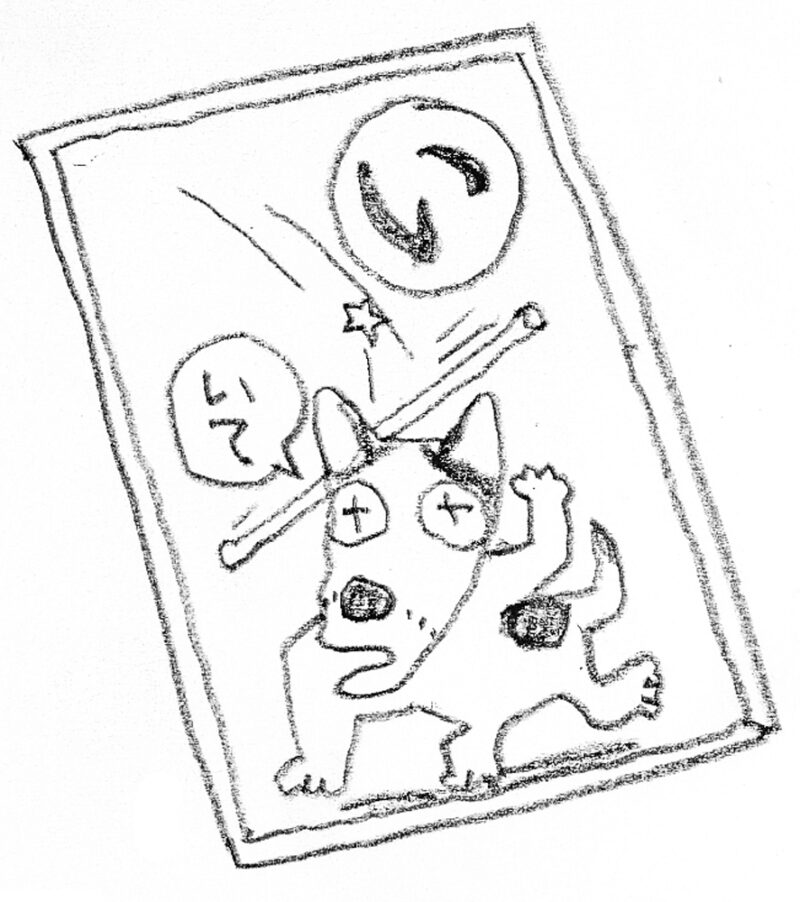今や、すべての日本人は、国語の基礎をアイウエオ・カキクケコの五十音で習ってますから、「いろは歌」といっても解らないようになりました。江戸末期・明治初期の頃(百四十年前)には、子どもたちは寺子屋(今の学習塾)で、文字の読み書きを「いろはにほへと」で手習いしてました。四十八文字の仮名を重複せず一度だけ使った七五調の歌です。
「色は匂へど散りぬるを 我が世誰ぞ常ならむ 有為の奥山今日越えて 浅き夢みし酔ひもせず」終わりに「ん」をつけて四十八文字にします。
お正月には「カルタ取り」で遊びましたが、それもいろは順で、(い)犬も歩けば棒に当たる、(ろ)論より証拠、(は)花より団子、そのほか(ら)楽あれば苦あり、(ゆ)油断大敵など、今でもよく聞く諺のようなものが出てきます。
明治中期に、ある新聞社が新しいいろは歌を公募したところ、何百首もの投稿があって、その一等賞には小学校の教員、坂本氏の作品が選ばれました。
「鳥鳴く声す夢覚ませ 見よ明け渡る東を 空色栄えて沖つ辺に 帆船群れ居ぬ靄の中」この作品を別名「とりな歌」といいます。
なんだ一体、今回は! 学校のお勉強じゃあるまいし、教科書とか辞書に書いてあるのをただ写しただけじゃん。まさに「あほらしや 知ってることを言いたがる 思いつくこと皆古くなる」じゃ。ドーモスイマセン。